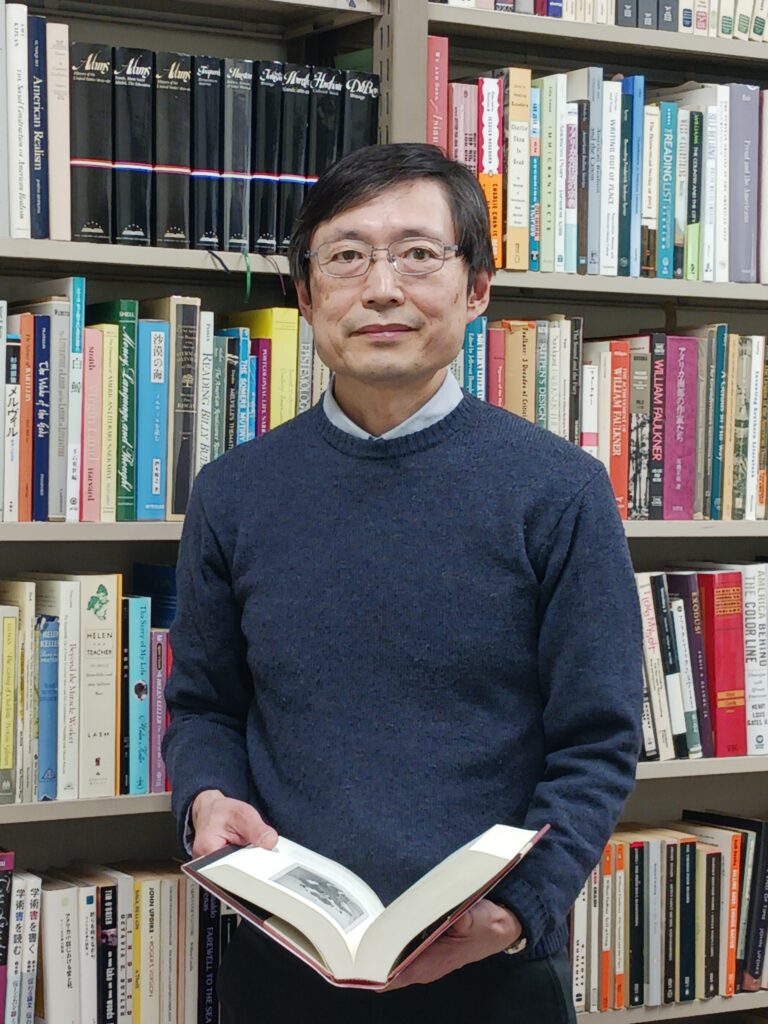ご挨拶
5つの専攻に分かれた大阪大学人文学研究科のなかでも、言語文化学専攻は、その教育目標に「今日ますます多文化・多言語社会へと変貌していく世界を理解し、得られた知見を広く社会に発信することにより、国家・民族・文化間の軋轢や紛争、温暖化現象などの環境問題や人口問題などの深刻化した問題の解決に貢献できる人材育成を目指します」とうたっているように、今日的な課題に幅広い観点から取り組むことを前面に掲げ、それを反映した組織づくりをしています。本専攻には3つの分野があり、それぞれに2つの講座を配しています。各分野は独自の視座から、言葉と文化に関わる諸問題に取り組むべく、教育や研究を行なっています。
いま私たちが直面している「今日的な課題」には、言語や文化に絡んだものが数多くあります。身近な例を挙げれば、SNSで使われる言葉が人の心をつなげる役割を果たす一方、分断や亀裂を時には意図的に深め、社会を不安定にし、政治の在り方に好ましからざる影響を及ぼしうることが憂慮されています。また、日本や他の国々で起きている少子高齢化のような現象は、男性と女性の立場や認識の違いといったジェンダーに関わる問題も浮き彫りにしますが、同時に、社会を維持するため新たに迎え入れた異なる文化や言語をもった人たちとどう付き合っていくか、という別の課題もクローズアップします。さらに目を転じれば、いま世界で起きている戦争や紛争もまた、お互いの文化や歴史を尊重しないことから芽生えた不信と憎悪の産物であるといえます。文化や言葉を異にする他者を知ろうとすること。それぞれの立ち位置から互いに学び合おうとすること。そんな姿勢が、人と人との間の軋みをやわらげ、平和で心豊かな未来を創っていくための鍵となるはずです。
本専攻が研究対象として取り上げる素材はそれぞれに異なり、実に多岐にわたっていますが、人文学の原点ともいえる〈言語と文化〉にかかわる研究であるという点では共通しています。この専攻で学ぶ大学院生は、自身の研究上の興味・関心がどのようなものであろうと、それが上に述べたような今日的な課題とどんな形でつながりうるかを考えつつ、研究に取り組むことになります。一般に学術研究というものは、自らの知的好奇心を満たしたいという衝動が出発点となりますので、その気持ちは大切にしなければなりません。しかし、この研究で得られた成果は、最終的には、口頭発表や印刷物として公表され、フィードバックを受けることになります。そうである以上、研究活動は独りよがりの愉しみごとで終わらず、何らかの形で他者との接点をもつ営みとなります。自身が行うこの研究は、他の人にとって、社会にとって、どんな意味があるのかを常に考えなければならないゆえんです。
この文章を読んでいる皆様のなかには、本専攻で言語や文化に関連した研究をしたいと考える人も多くいらっしゃると思います。そのような方は、ある特定の関心をすでにもっておられるはずであり、研究科にご入学されたならば、その関心に関連した授業や指導を受け、調査をし、先行研究を読み、分析を行ない、新しい知見に到達されることでしょう。それはまるで、井戸を深く深く堀っていくことで、飲み水の新たな源を掘り当てるような営みです。そもそもどのあたりに水源がありそうなのか、位置を突き止めるのがとても難しいでしょうし、どんな道具を使いどのように掘り進めればいいのか、これまでのやり方では通用しないこともあるでしょう。
水源の位置を探り、掘削をするための方法は、さまざまな研究領域から学んで、その都度自ら編み出していく必要があります。そのために、本専攻は領域横断的な研究・教育ができる仕組みを用意しています。すでに述べたように6講座に分かれているものの、大学院生は特にどの講座に属するわけではありません。これを学びたいと思った分野・講座の授業を自由に受講できるようになっています。また、主と副の指導教員をつけますが、これらの教員に限らず、専攻のどの教員からも指導・相談を受けることができます。そのような指導上の人間関係の風通しのよさも、この専攻の特色です。
努力の末に到達した研究成果という水源から飲む水の味は格別ですが、それを独り占めするのでなく、渇きに苦しむ他の人たちにも差し出してあげることを忘れてはなりません。もし、じゅうぶんな数の人の渇きを癒すことができなければ、より大きな水源を求めて、また新たな探索が開始されます。その際には前回の試みが少しは役に立ってくれますが、新たに学びなおす必要はなくならない。そうした作業の果てのない繰り返しが、私が日頃抱いている〈研究〉と呼ばれる営みのイメージです。ご自身の好奇心を大切に育てながら、核とみなすディシプリンに加え、これまで学んだことのない研究の領域や方法から学びつつ、新たな水源を探そうとする方を歓迎します。言語と文化に関する深い教養や情報活用の能力を修得することで、多様な問題にねばり強く取り組もうとする皆様を、本専攻は支援いたします。
いま私たちが直面している「今日的な課題」には、言語や文化に絡んだものが数多くあります。身近な例を挙げれば、SNSで使われる言葉が人の心をつなげる役割を果たす一方、分断や亀裂を時には意図的に深め、社会を不安定にし、政治の在り方に好ましからざる影響を及ぼしうることが憂慮されています。また、日本や他の国々で起きている少子高齢化のような現象は、男性と女性の立場や認識の違いといったジェンダーに関わる問題も浮き彫りにしますが、同時に、社会を維持するため新たに迎え入れた異なる文化や言語をもった人たちとどう付き合っていくか、という別の課題もクローズアップします。さらに目を転じれば、いま世界で起きている戦争や紛争もまた、お互いの文化や歴史を尊重しないことから芽生えた不信と憎悪の産物であるといえます。文化や言葉を異にする他者を知ろうとすること。それぞれの立ち位置から互いに学び合おうとすること。そんな姿勢が、人と人との間の軋みをやわらげ、平和で心豊かな未来を創っていくための鍵となるはずです。
本専攻が研究対象として取り上げる素材はそれぞれに異なり、実に多岐にわたっていますが、人文学の原点ともいえる〈言語と文化〉にかかわる研究であるという点では共通しています。この専攻で学ぶ大学院生は、自身の研究上の興味・関心がどのようなものであろうと、それが上に述べたような今日的な課題とどんな形でつながりうるかを考えつつ、研究に取り組むことになります。一般に学術研究というものは、自らの知的好奇心を満たしたいという衝動が出発点となりますので、その気持ちは大切にしなければなりません。しかし、この研究で得られた成果は、最終的には、口頭発表や印刷物として公表され、フィードバックを受けることになります。そうである以上、研究活動は独りよがりの愉しみごとで終わらず、何らかの形で他者との接点をもつ営みとなります。自身が行うこの研究は、他の人にとって、社会にとって、どんな意味があるのかを常に考えなければならないゆえんです。
この文章を読んでいる皆様のなかには、本専攻で言語や文化に関連した研究をしたいと考える人も多くいらっしゃると思います。そのような方は、ある特定の関心をすでにもっておられるはずであり、研究科にご入学されたならば、その関心に関連した授業や指導を受け、調査をし、先行研究を読み、分析を行ない、新しい知見に到達されることでしょう。それはまるで、井戸を深く深く堀っていくことで、飲み水の新たな源を掘り当てるような営みです。そもそもどのあたりに水源がありそうなのか、位置を突き止めるのがとても難しいでしょうし、どんな道具を使いどのように掘り進めればいいのか、これまでのやり方では通用しないこともあるでしょう。
水源の位置を探り、掘削をするための方法は、さまざまな研究領域から学んで、その都度自ら編み出していく必要があります。そのために、本専攻は領域横断的な研究・教育ができる仕組みを用意しています。すでに述べたように6講座に分かれているものの、大学院生は特にどの講座に属するわけではありません。これを学びたいと思った分野・講座の授業を自由に受講できるようになっています。また、主と副の指導教員をつけますが、これらの教員に限らず、専攻のどの教員からも指導・相談を受けることができます。そのような指導上の人間関係の風通しのよさも、この専攻の特色です。
努力の末に到達した研究成果という水源から飲む水の味は格別ですが、それを独り占めするのでなく、渇きに苦しむ他の人たちにも差し出してあげることを忘れてはなりません。もし、じゅうぶんな数の人の渇きを癒すことができなければ、より大きな水源を求めて、また新たな探索が開始されます。その際には前回の試みが少しは役に立ってくれますが、新たに学びなおす必要はなくならない。そうした作業の果てのない繰り返しが、私が日頃抱いている〈研究〉と呼ばれる営みのイメージです。ご自身の好奇心を大切に育てながら、核とみなすディシプリンに加え、これまで学んだことのない研究の領域や方法から学びつつ、新たな水源を探そうとする方を歓迎します。言語と文化に関する深い教養や情報活用の能力を修得することで、多様な問題にねばり強く取り組もうとする皆様を、本専攻は支援いたします。
2025年4月
言語文化学専攻長
里内克巳